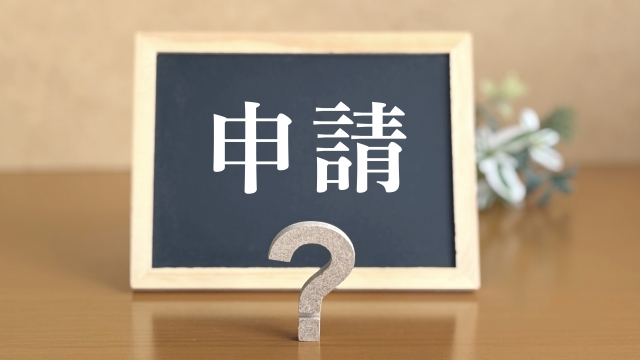障がい福祉事業をスタートさせるための「指定申請」スケジュールを徹底解説。希望する開所日から逆算して、物件確保や人員採用、書類提出のベストなタイミングを時系列で整理します。
障がい福祉事業を始めるにあたって、多くの方が最初に突き当たる壁が「いつ、何をすれば希望の日にオープンできるのか?」というスケジュールの問題です。
指定申請は、書類を出せばすぐに許可が出るわけではありません。行政による厳格な審査期間があるため、「開所希望日」から逆算した緻密な計画が不可欠です。
本記事では、名古屋市での開業をモデルケースに、理想的なスケジュール感を確認していきましょう。
1. 指定申請スケジュールの全体像
まずは、標準的な流れを把握しましょう。一般的に、準備開始から開所までには最低でも半年、余裕を持つなら1年を見ておくのが理想的です。
ステップ①:【6ヶ月前〜】事業構想と法人設立
障がい福祉サービスは、個人事業主では行えません。
- 法人設立: 株式会社、合同会社、一般社団法人などを設立します。定款の「事業目的」に適切な文言が入っているかが重要です。
- 事業計画: どのサービス(就労支援、グループホーム等)を、どこで行うかを固めます。
ステップ②:【5ヶ月前〜】物件探しと事前相談
ここが最大の難所です。
- 物件確保: 建築基準法や消防法の要件を満たす物件を見つけます。
- 名古屋市への事前相談: 名古屋市の場合、指定申請の前に「事前相談」の予約が必要です。物件の図面を持参し、設備基準を満たしているか確認を受けます。
ステップ③:【3〜4ヶ月前】人員の確保
- 有資格者の採用: サービス管理責任者(サビ管)や児童発達支援管理責任者(児発管)など、配置基準を満たすスタッフを確定させます。実務経験証明書の収集もこの時期に行います。
ステップ④:【2ヶ月前】指定申請書の提出
- 書類の提出: 名古屋市では通常、**開所予定日の前々月の末日(または指定の締切日)**が申請の締め切りとなります。
- 例:4月1日開所希望なら、1月末までに全ての書類を不備なく受理される必要があります。
ステップ⑤:【1ヶ月前】現地調査と審査
- 行政による確認: 書類審査と並行して、実際に事業所の設備が基準通り整っているか、行政担当者による現地確認が行われる場合があります。
2. 失敗しないための「逆算」のポイント
スケジュールが狂う原因の多くは、以下の2点に集約されます。
物件の改修・消防工事
「賃貸契約をしてから、消防設備の設置に時間がかかることが分かった」というケースは非常に多いです。工事期間を見込んでいないと、家賃だけが発生し、開所日が数ヶ月ずれ込むリスクがあります。
スタッフの「実務経験証明書」
採用予定者が以前の職場から証明書を取り寄せるのに時間がかかることがあります。「書類が揃わないから申請が出せない」という事態を避けるため、早めの依頼が鉄則です。
3. まとめ:スケジュール管理が開業の成否を分ける
障がい福祉事業の開業は、パズルのピースを一つひとつ埋めていくような作業です。特に名古屋市のルールは細かく、事前相談の予約枠が埋まっていて数週間待ちになることも珍しくありません。
「4月に開所したいから、1月から動き出せばいいだろう」と思っていると、間に合わない可能性が高いのがこの業界の難しいところです。
4. 行政書士からのアドバイス
はじめての開業では、カレンダーを見ながら「今、何をすべきか」を正しく判断するのは困難です。
当事務所では、お客様の「理想の開所日」を伺った上で、無理のないオーダーメイドのスケジュール表を作成し、伴走支援を行っております。
- 物件を契約する前に確認してほしい
- 名古屋市の事前相談に同行してほしい
- 複雑な書類作成をプロに任せて、採用や集客に専念したい
そんな方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
免責事項・注記
- 本記事に記載のスケジュールはあくまで一般的な目安であり、申請書類の不備、物件の状況、行政の審査状況等により前後します。
- 名古屋市独自のルールや最新の改正内容については、必ず最新の「指定申請の手引き」をご確認ください。
- 具体的なスケジュール作成については、専門家へ個別にご相談いただくことをお勧めします。
行政書士わたなべオフィス 名古屋市の障がい福祉事業指定申請・運営をトータルサポート