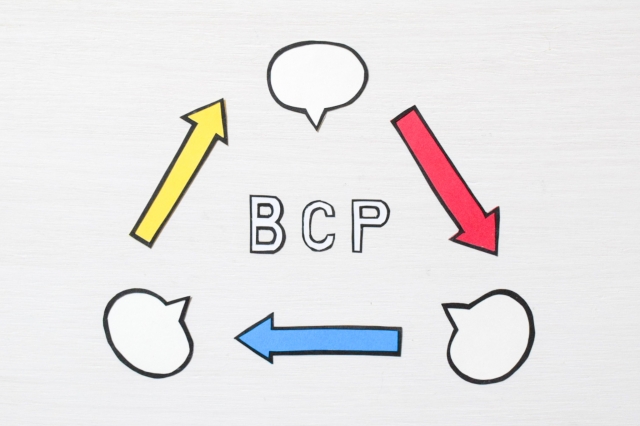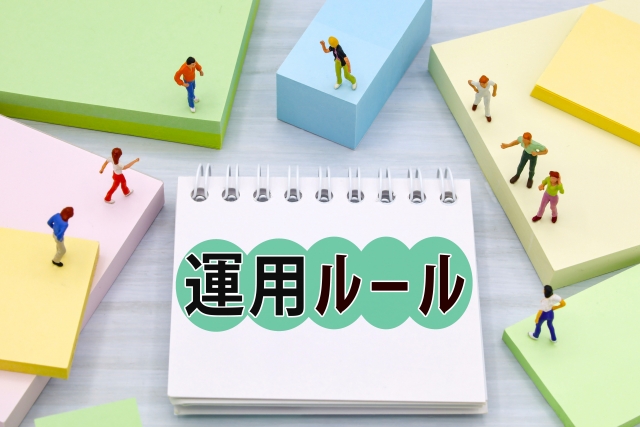障がい者グループホーム(共同生活援助)の売上を左右する「障害支援区分」と「基本報酬」の仕組みを徹底解説。区分ごとの報酬単価の違いや、安定運営のために経営者が知っておくべきポイントを専門家がまとめました。
障がい者グループホーム(共同生活援助)を運営する上で、避けて通れないのが**「障害支援区分」と「基本報酬」**の関係です。
「入居者が満室になれば安心」と思われがちですが、実は入居される方の「区分」がいくつかによって、事業所に入る報酬(売上)は大きく変動します。安定した経営を続けるために、まずは報酬の仕組みを正しく理解しましょう。
1. 報酬を決定する「障害支援区分」とは?
障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態に応じて、どの程度の支援が必要かを示す指標です(区分1〜6)。
グループホームの基本報酬は、この**「入居者の平均区分」や「個人の区分」**に応じて段階的に設定されています。
- 区分の数字が大きい(例:区分4以上): 支援の必要度が高いため、報酬単価が高くなる。
- 区分の数字が小さい(例:区分2以下): 支援の必要度が比較的低いため、報酬単価は抑えられる。
2. 運営形態による報酬の違い
グループホームには、大きく分けて3つのタイプがあり、それぞれ報酬体系が異なります。
- 介護サービス包括型: 事業所のスタッフが家事や介護をすべて行うタイプ。多くのグループホームがこの形態です。
- 外部サービス利用型: 家事などは事業所スタッフが行い、重度の介護が必要な場合は外部のヘルパーを利用するタイプ。
- 日中サービス支援型: 常時介護が必要な方向けに、日中もホームで過ごせるよう手厚い人員を配置するタイプ(区分が高い方が対象)。
3. 経営者が意識すべき「売上のシミュレーション」
グループホームの経営を安定させるポイントは、**「自所のターゲット(支援の専門性)と報酬のバランス」**にあります。
- 重度の方(区分4〜6)を受け入れる場合: 報酬単価は高いですが、その分「夜勤職員の増員」や「医療的ケアの体制」など、人件費等のコストが増大します。
- 軽度の方(区分1〜3)を受け入れる場合: 単価は低めですが、自立支援に特化することでスタッフの負担を抑え、少人数での運営が可能です。
4. 安定運営のための3つのチェックポイント
- 「平均区分」の把握: 事業所全体の平均区分によって、算定できる加算の種類が変わることがあります。
- 区分変更への対応: 入居後に状態が変化し、本来の支援内容と区分が合わなくなった場合は、自治体へ区分変更の申請を検討するよう、利用者様や相談支援専門員と連携することが大切です。
- 加算の積み上げ: 基本報酬だけでなく、人員配置や専門性を評価する「加算」を漏れなく取得することが、収支安定の鍵を握ります。
5. まとめ
グループホームの報酬体系は非常に複雑で、名古屋市や愛知県の最新の報酬改定によっても変動します。
「誰を、何人受け入れるか」という計画が、そのまま「事業を継続できるか」に直結します。収支計画を立てる際は、単なる「満室時」の計算だけでなく、区分ごとのシミュレーションを事前に行っておきましょう。
行政書士わたなべオフィスができること
当事務所では、指定申請に必要な「収支予算書」の作成や、報酬単価の確認をサポートしております。
「自分の事業計画で、基本報酬はいくらになる?」 「最新の報酬体系だと、どの加算が狙えそう?」
制度上の「売上の立て方」を正しく把握することは、開業準備の第一歩です。複雑な報酬算定の仕組みを整理し、確実な申請をお手伝いいたします。
免責事項・注記
- 本記事に記載の報酬の仕組みは2026年1月現在の法令に基づいています。
- 実際の報酬額は、自治体の地域区分(名古屋市は1級地など)によって補正されるため、詳細な計算は必ず最新の報酬算定構造をご確認ください。
行政書士わたなべオフィス 名古屋市のグループホーム経営・指定申請を実務でサポート
▶開業相談はこちらから